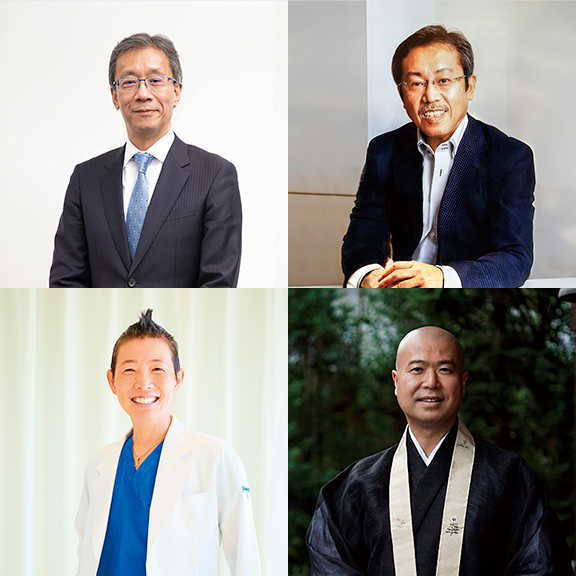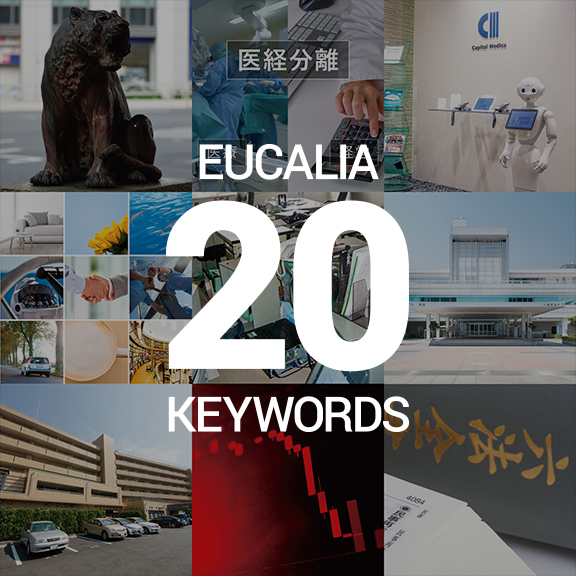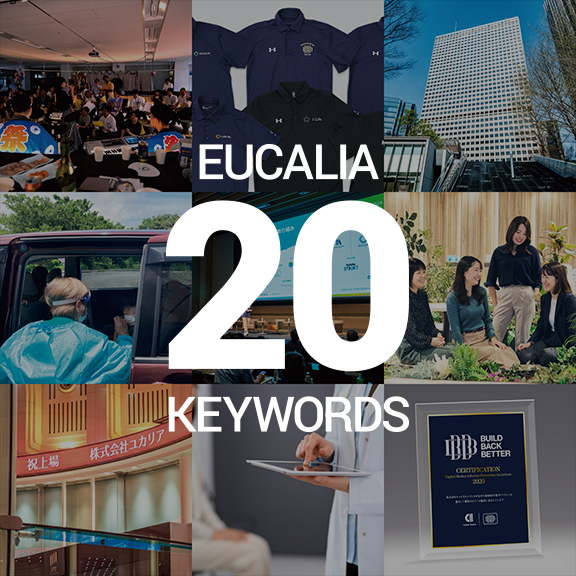創業ストーリー
Founding Story

20年間の経験により病院経営の
あらゆる課題を解決するユカリアは唯一無二の存在です。
おかげさまで、2025年2月14日にユカリアは設立20年を迎えることができました。今日までの歩みを支えてくださったすべての方々に、まずは厚く御礼を申し上げます。
日本は今、本格的な超高齢社会に突入しています。社会保障費は増加の一途をたどり、医療・介護給付費は、2022年に59兆円に達し、2040年には94兆円にまで膨らむと予測されています。私たちがビジョンとして掲げている「ヘルスケアの産業化」の実現を通じて、社会保障費の適正化と生活の質の向上を実現することは、もはや我々の社会的責務であると考えています。
これまでの20年間、ユカリアは病院の再建・変革に力を注ぎ、医療現場の活性化を推し進めてきました。現在までに、ヒト・モノ・カネを投入し、徹底的な伴走型支援により再建した病院数は40を超えています。決して平坦な道のりではありませんでしたが、ここであらためて、ユカリア20年の軌跡を振り返ってみたいと思います。
振り出しは「ファンド事業」
ユカリアの出発点は、ファンド事業でした。27歳で起業するまで、私は大手監査法人に勤務し、公認会計士として流通・小売業界の監査業務を担当していました。しかし、「過去の終わった数字ではなく、未来の数字を創りたい」という想いが強まり、2002年に「虎ノ門キャピタル」を創業しました。
「儲かりそうな事業には何でも投資する」「面白そうなことは何でもやる」―そんなスタンスで始めたプロフェッショナルファームは、やがてファンド事業に本格的に乗り出し、運用資産は1,000億円を超えるまでに成長しました。
ところが、当時すでに1兆円規模のファンドが多数存在していて、「何でもやる」という方針では勝負にならないと痛感しました。我々が「これなら本気で勝てる」と思えるフィールドを探るべく、複数の分野を研究した結果、最終的に「ヘルスケア」を選ぶに至ったのです。
その決断の背景には、強い使命感がありました。
病院の不良債権処理に関わる中で医療の現場に触れ、多くの解決すべき課題を目の当たりにしました。私が以前担当していた流通の大手企業には明快な経営戦略と現実的な事業計画がありましたが、病院にはそれが見られず、旧態依然とした非効率な構造が残っていました。
その一方で、医師や看護師たちは高い専門性、倫理観、そして志を持って懸命に働いていました。その姿に触れたとき、公認会計士という立場から経営を見てきた自分の知見を持って、医療従事者の力になりたいと心から思ったのです。
キャピタルメディカ設立
こうして、ヘルスケア分野に特化するため、2005年にキャピタルメディカ(現在のユカリア)を設立しました。医療は規制業種でもあるため、最初から虎ノ門キャピタルとは別法人として運営することにしました。
最初の案件は、メガバンクから不良債権として引き取った3つの病院の再建でした。中でも、最初に経営支援に入った病院は今でも忘れられません。不透明な会計処理の是正に着手したところ、従来のやり方を変えたくない事務長から猛烈な抵抗を受けました。
今となっては笑い話ですが、ある日その病院を訪れると、病棟の柱が壊されていたのです。目撃した職員の証言から、その事務長の仕業だとわかりました。重機で柱を破壊し、我々を撤退させるために病院の資産価値を意図的に落とそうとしたのです。
しかし、我々は一歩も引きませんでした。悪戦苦闘の末、最終的には事務長に退任いただき、その病院を地域有数の精神病院として再生させることに成功しました。現在では、自治体から優良指定を受けるまでになっています。
このように、再生にまつわる物語はどの病院にも存在します。そして20年間の経験により積み重ねられてきた、「選ばれる病院」に生まれ変わるためのノウハウは、ユカリアの大きな財産となっています。単なるコンサルティングにとどまらず、運転資金の貸し付けから、地域連携支援、建て替え支援まで、病院経営のあらゆる課題を総合的に解決するユカリアのビジネスモデルは、唯一無二であると自負しています。

コロナ禍を通じて社会の公器としての自覚を強め、
大きく成長できた
「運」の後押しもあり、乗り越えた2度の経営危機
ユカリアが今の姿に成長するまでに、順風満帆だったわけではありません。これまで2度、大きな経営危機に直面しました。2008年のリーマンショックと、2020年のコロナ禍です。
リーマンショック以前、ユカリアは投資ファンドの資金で病院へリスクキャピタルを提供していました。しかし、リーマンショックが起きると、その余波で機関投資家から「病院を売って、資金を返してほしい」という要請が相次ぎました。経営再建中の病院をすぐに売却できるはずもありません。追加出資のない病院の資金繰りは急激に悪化し、ユカリアの経営会議では30分間誰も発言できず沈黙が続くほど、再生ファンド事業は追い詰められていました。
そのような状況の中、幸運にも長い付き合いのあるメガバンクが資金支援を決断。これによりファンドの持ち分をすべて買い取り、「病院のために働くユカリア」へと本当の意味で生まれ変わる転機となりました。あの出来事がなければ、今のユカリアは存在していなかったかもしれません。
2020年には、コロナ禍によって全国の病院が機能不全に陥りました。ユカリアの提携医療法人も例外ではなく、収益は激減。そんな中、国内初の緊急事態宣言が発出された同年4月に、提携医療法人の1つである埼玉県川口市の川口工業総合病院が、民間病院として初となるコロナ専門病棟の開設を決断しました。
川口市内には、3つの基幹病院があるのですが、川口工業総合病院がロックダウンし、済生会川口総合病院もその10日前にロックダウン。そこで、川口工業総合病院がコロナ患者を、その他の患者は残る川口市立医療センターが受け持つという役割分担で、川口市民60万人を守ることが決まりました。
ユカリアに在籍する医師や看護師も現場に赴き、医療従事者に対しても粘り強く説明を重ね、コロナ患者の受け入れに踏み切りました。経営状況は厳しかったものの、「国難に立ち向かい、地域住民に奉仕する」という病院とユカリアの覚悟が幸運を引き寄せたのかもしれません。結果として6月の補正予算で病院への緊急融資が決定し、9月からはコロナ病床を持つ病院に対する補助金が始まったことは、全国の提携医療法人が地域で活躍する後押しとなりました。この経験を通じて、ユカリアは社会の公器としての自覚をより一層強め、会社として一回りも二回りも大きく成長できたと感じています。
三沢英生との出会い
この時期、もう1つ大きな転機がありました。2020年4月、三沢英生がユカリアに加わったのです。外資系金融やスポーツの世界で活躍してきた彼が入社早々、「ユカリアはこれだけ社会に貢献する良いことをしているのだから、もっと堂々と社会に発信していきましょう」と力強く背中を押してくれました。その言葉には私自身、大いに勇気づけられました。嬉しかったですね。
彼は今、私のビジョンを具現化する推進力として、代表取締役社長を務めてくれています。
実兄の死
事業領域が広がり、成長するにつれて、「変革を通じて医療・介護のあるべき姿を実現する」というミッションをより強く意識するようになりました。そうした変化の根底には、実兄の死も大きく影響しています。厳格な父のもとから兄は10代で家を出て行きました。再会したのは、キャピタルメディカ設立時です。社員が10名にも満たなかった頃、IT業務全般を兄が担ってくれました。いわば陰の功労者でした。
そんな兄が癌に罹患し、2017年に世を去った。兄の「ペイシェントジャーニー」(患者が病気を認知し、診断・治療を進める際に、どのように感じ、考え、行動するのかの道筋)を見届ける中、多くの医療従事者に助けられ、深い感謝の念を抱くと同時に、「正しい医療が現場に届いていない」現実にも気づかされました。このとき私は、医療現場の変革とは、単なる「ビジネス」ではなく「社会的使命」そのものであると痛感するとともに、過酷なペイシェントジャーニーをよりよいものにしなければならないと決意したのです。
未来のヘルスケアに向けて
この「社会的使命」を果たすために、私はユカリアをさらに成長させたいと考えています。
そして今、ヘルスケアのさらなる進化を私は感じています。これからの時代に向けて大切にしたいのが、「セルフメンテナンスの重要性」です。今後、ヘルスケア産業においては「病院や医師に頼るだけではなく、自分自身で健康を管理する力」がより重視されるようになると考えています。
特に注目しているのが、米国で進展している「エピゲノム解析」です。これは“後天的に変化するゲノム”という意味で、つまり“変えられる遺伝情報”。これを解析することで、かなり高精度に寿命の予測が可能になりつつあります。私も実際にエピゲノム解析を受けたのですが、現在の身体が何歳相当なのか、推定寿命はどれくらいかを知る体験に、ワクワクした自分がいました。こうした取り組みが当たり前になれば、人々は癌をはじめとする重篤な病気に罹患する前から、健康な未来への備えができるかもしれません。遺伝情報をもとに、誰もが正しい医療にまっすぐにたどり着ける時代が、きっと訪れる。ヘルスケアの未来には、確かな希望があると私は信じています。
今年3月に私は代表の座を退き、取締役会長となりました。これからは代表取締役社長の三沢に舵を託しつつ、創業者としてビジョン・ミッション、そして「三方良し」の世界観を実現するために、引き続き積極的に貢献してまいります。
ユカリアが今後30年、50年、100年と、社会に必要とされる存在であり続けるために、私自身も歩みを止めることなく、前進を続けていく所存です。
今後とも、皆様の変わらぬご支援を心よりお願い申し上げます。
取締役会長 古川 淳