虎の巻その35 診療単価を高めて病院経営を改善するための実践ガイド

こんにちは。虎兄(とらにぃ)です。病院経営コラム「病院経営~虎の巻~」。
病院の収益は「患者数 × 診療単価」で成り立っています。黒字化を目指すには、「患者数の増加」、「診療単価の向上」、そして「費用の削減」という3つの方法がありますが、どれを優先すべきか悩む方も多いでしょう。日々の業務の中で経営課題に直面しつつも、具体的なアプローチ方法に困る場面が多いのではないでしょうか。
今回のコラムでは、特に「診療単価の向上」に焦点を当て、「医学管理料」「リハビリテーション」「手術」の診療区分ごとに、収益改善のポイントと実践の方法をわかりやすく解説します。
医学管理料:見落としがちな収益源を掘り起こせ
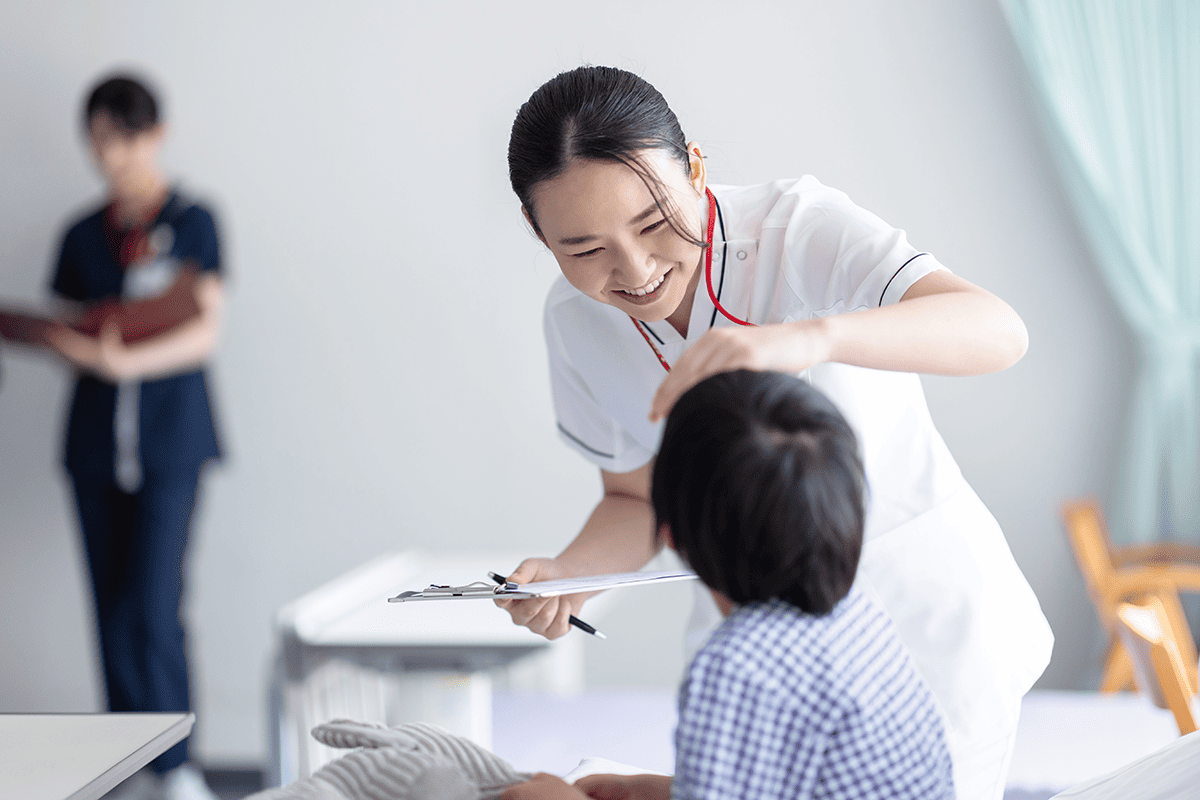
医学管理料は、患者への指導や管理など「目に見えない医療行為」に対して評価される項目ですが、50種類以上あるために見逃されがちで、収益機会を逃していることも少なくありません。例えば、てんかん指導料や難病外来指導管理料など、特定疾患療養管理料よりも高い点数が設定されている管理料もありますが、「とりあえず特定疾患」となってしまうことが多いのが実情です。
始めに行うことは現状分析ですが、その出発点は医事課から管理料別件数のデータを入手し、病院機能と算定内容が一致しているかを確認することです。利用が可能であれば、オープンデータと照合することで自院の立ち位置を把握してください。その上で、主病名の見直し、カルテ記載の徹底、勉強会の開催といった改善施策を講じ、定期的なモニタリングによって収益への影響を検証します。
リハビリテーション:加算の取りこぼしを防げ

リハビリテーションは特に単価が高く設定されている診療区分です。1単位(20分)あたり77点(廃用症候群リハビリテーション料Ⅲ)から最大245点(脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ)(※いずれも2025年度時点の診療報酬点数)と幅広く、施設基準や疾患別の要件に応じて得られる収益が大きく変わります。初期加算や早期加算、総合計画評価料などは比較的簡単に取得が可能でありながら、実際には見落とされがちな項目です。
現場の運用実態に即して、単価だけでなく患者数なども含めた継続的な分析を行うことと、月次モニタリングでKPIと実績の乖離を把握する体制を構築することを大事にしてください。そのためには、医事課や診療情報管理部門と連携しつつ、現場との信頼関係を築きながら改善を進めることが成功のカギとなります。
手術:高稼働を維持することで、高単価な手術料の収益を最大化せよ
手術は診療単価の中でも突出して高く、病院全体の収益へのインパクトが大きい診療区分です。整形外科では特定保険材料の割合が高く、外科では麻酔関連費用が収益に大きな影響を与えます。
手術料の収益性を高めるためには、自院で行う手術の内容とその単価を把握することと合わせて、手術室のより高い稼働を目指すことが重要です。手術枠の設定と実際の稼働状況を診療科別に分析し、入れ替え時間の短縮や手術枠のバランスの見直しなどを行うことで、無理なく稼働率を改善できます。また、医療機能や規模が近い病院と比較し、手術室の運用における改善点を明確にすることも有効です。
共通する重要ポイントは、現場との連携と継続的なモニタリング
いずれの区分においても共通するのは、「現場とのコンセンサス」と「継続的なモニタリング」の重要性です。改善策は医師や看護師、医事課、リハビリスタッフといった関係者の協力があってこそ定着し、効果が持続します。また、勉強会の開催などによって現場と経営層の対話を活性化することで、診療単価の向上が患者満足にもつながるという視点を共有することが大切です。
これらの取り組みは、組織づくりにおける「見える化」「仕組み化」の実践にほかなりません。「見える化」によって課題を明確にし、関係者が共通認識を持って改善策を検討できるようになります。そして、「仕組み化」によって改善策をスムーズに推進し、結果を集約・評価する体制が整います。経営課題を乗り越え、環境変化にも柔軟に対応できる組織づくりの第一歩です。
まとめ
経営改善に向けて「何から始めれば良いか分からない」という方は、まず上記で紹介した医学管理料とリハビリテーション、手術の3区分の取り組みから始めてみてはいかがでしょうか。
今回は、診療単価を上げる観点から具体的な経営改善に向けた方策を紹介しました。「現場のコンセンサス」と「継続的なモニタリング」による「見える化」「仕組み化」を常に意識して進めるようにしてください。



